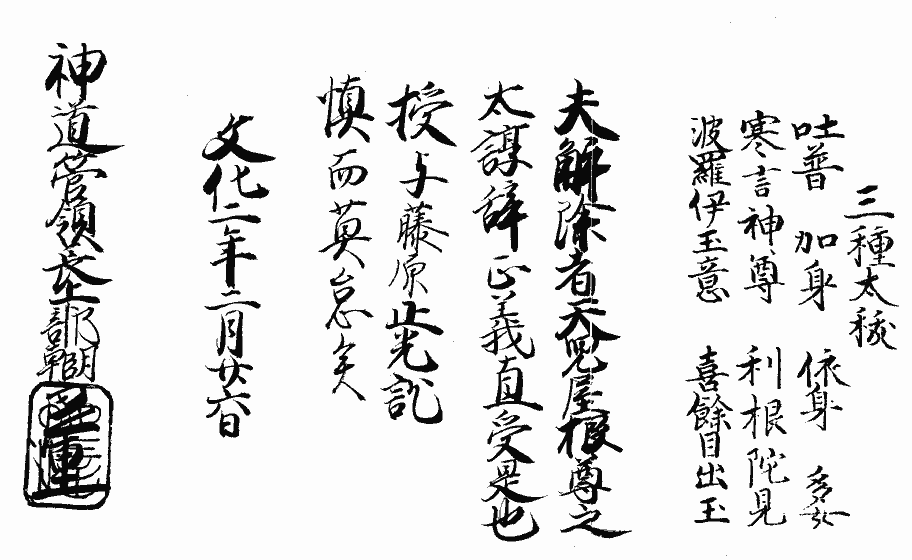戞嶰復丂墑嫕墢婲偲曚愊恄幮
戞侾愡丂峕屗枊晎偺恄摴惌嶔偲嶳暁懳嶔側傜傃偵媑揷恄摴
尩偟偄嶳暁婯惂偲恄摴惌嶔
丂墑嫕榐婲偵偮偄偰峫偊傞慜偵丄峕屗枊晎偺恄摴惌嶔偲嶳暁懳嶔丄偦傟偵媑揷恄摴偵偮偄偰尒偰偍偔昁梫偑偁傞丅偲偄偆偺傕丄姲暥墢婲傕墑嫕墢婲傕丄媑揷恄摴偺尩偟偄恄怑摑惂偵尃暫塹堦懓偑懳墳偡傞偨傔偵嶌傜傟偨偲峫偊傜傟傞偐傜偱偁傞丅
丂姲暥墢婲偼孎栰廋尡宯偺嶳暁偱偁偭偨尃暫塹堦懓偑丄枊晎偺惌嶔偵傛偭偰嶳暁偐傜幮恖偵揮姺偡傞偙偲傪梋媀側偔偝傟偰嶌惉偝傟偨恄榖偱偁傞丅扢宯恾傕偦偺姲暥墢婲偵偲傕側偭偰曇傑傟偨尃暫塹堦懓偺擭戙婰偱偁傞丅
丂偦偟偰摗暫塹偲偺懳棫傪崕暈偟丄偲傕偐偔傕幮恖偵曄恎偟偨尃暫塹堦懓偼尃暫塹偑姶摼偟偨棾捾尃尰傪棾捾嶳忋偵釰傞偙偲偵側偭偨丅
丂偟偐偟丄偦偺棾捾尃尰偑嵞傃媑揷恄摴偵傛偭偰恄奿偺曄峏傪媮傔傜傟偨寢壥丄嶌惉偝傟偨偺偑墑嫕椢婲側偺偱偁傞丅
丂尃暫塹堦懓偼姲暥偐傜墑嫕偺偍傛偦俉侽擭偺娫偵丄擇搙偵傢偨傝媑揷恄摴偲偄偆嫄戝側夦暔偺慜偵旼傪孅偟偨丅
丂傑偨丄偦偺媑揷壠偑恄摴奅偵埿惃傪怳傞偆偙偲偑偱偒偨偺傕丄攚屻偵峕屗枊晎偺恄摴惌嶔偲嶳暁懳嶔偲偑偁偭偨偐傜偩偭偨丅偙傟傜偺枊晎偺惌嶔傕丄傑偨姲暥墢婲偲墑嫕墢婲偵戝偒側塭嬁傪梌偊偨丅
丂摽愳壠峃偼朙恇壠傪柵傏偟擔杮偺巟攝幰偲側偭偨偺偪丄栴宲偓憗偵奺庬偺朄搙傪惂掕偟偨丅惌帯揑偵偼晲壠彅朄搙傗嬛拞暲岞壠彅朄搙偑嫇偘傜傟傞偑丄暓嫵奅偵懳偟偰傕壠峃偑惗懚拞偐傜師乆偲奺廆偛偲偺朄搙傪惂掕偟丄帥堾婯惂傪奐巒偟偨丅偡側傢偪丄宑挿俈擭偺忩搚廆偵巒傑傝丄偦偺屻丄揤戜廆丄恀尵廆丄憘摯廆丄椪嵪廆側偳偱偁傞丅
丂偙傟傜帥堾朄搙惂掕偺栚揑偼丄帥堾傪廆嫵偺榞偺拞偵墴偝偊崬傒丄惌帯傊岥弌偟偡傞偙偲傪屌偔嬛偠傞偙偲偩偭偨丅婨撪偺戝帥堾偑朙恇曽偲寢傫偱丄斀摽愳惃椡壔偡傞偙偲傪嫲傟偨偐傜偱偁傞丅
丂暯埨帪戙偐傜墑楋帥傗嶰堜帥側偳偺憁暫偑丄悢傪棅傫偱挬掛偵嫮慽偟偨傝丄帪偺惌帯尃椡偵斀峈偡傞偙偲偼捒偟偔側偐偭偨丅枊晎偼帥堾偵偙傟傪嫋偝偢丄尩偟偄懺搙偱朷傓偙偲偵偟偨偺偱偁傞丅
丂忩巑恀廆偺杮婅帥偼愇嶳崌愴傪怐揷怣挿偲屳妏偵愴偭偨丅奺抧偵堦岦堦潉偑惗婲偟丄愴崙帪戙傪偄偭偦偆崿棎偝偣偨丅壠峃帺恎傕崱愳媊尦偺巰偵傛偭偰恖幙偺恎暘偐傜夝曻偝傟偨偑丄壀嶈偵婣忛偟偰娫傕側偔丄壠恇傜傪姫偒崬傫偩堦岦堦潉偵擸傑偝傟偨嬯偄宱尡偑偁傞丅
丂壠峃偼杮婅帥偲偄偆戝柤傪椊偖嫮戝側惃椡傪嶦偖偨傔偵丄偙傟傪搶惣椉杮婅帥偵暘妱偟偨偲偄傢傟偰偄傞丅
丂嶳暁傪懳徾偲偟偨嶳暁朄搙偑敪椷偝傟偨偺偼宑挿侾俉擭(1613)丄偦偟偰偙傟偵娭楢偡傞屼怗彂偺岞晍偼姲暥俀擭(1662)偱偁傞丅偙偺偙傠偐傜枊晎偼嶳暁懳嶔偵杮崢傪擖傟巒傔偨丅枊晎偼嶳暁偑帩偮婋尟傪嶡抦偟偰偄偨丅嶳暁偺帩偮慡崙帺嵼偺婡摦椡傪嫲傟偨丅
丂愄偐傜嶳暁偼曄憰偡傞偵偼奿岲偺巔側偺偩丅尮媊宱偼孼棅挬偺捛媮傪摝傟傞偨傔丄嶳暁偵巔傪曄偊丄曎宑埲壓偺廬幰偨偪偲墱廈偵摝傟偨丅斵傜偺摝朣偵偼孎栰傗媑栰丄搶杒偺塇崟嶳側偳偺嶳暁偺嫤椡偑偁偭偨偲偄傢傟傞丅
丂屆偔偼恜怽偺棎偺偝偄丄戝奀恖峜巕偼嵞婲傪恾傞偨傔丄愽暁偟偰偄偨媑栰偐傜旤擹偵擖偭偨丅偙偺偲偒偺峜巕傕嶳暁巔偩偭偨丅撿杒挬偺憟棎偱偼丄岇椙恊墹偼傗偼傝嶳暁偵曄憰偟偰孎栰偵擖偭偰偄傞丅
丂偙偺傛偆側惌帯斊傗楺恖丄斊嵾幰側偳偑嶳暁巔偱彅崙傪減渏偟丄奺抧偺摨椶偲楢棈傪庢傝崌偆偙偲傪曻抲偟偰偄偰偼丄偄偮枊晎揮暍偺婇偰偵寢傃偮偐側偄偲傕尷傜側偄丅偦偺摉帪丄慡崙偵偼枊晎偵晄枮傪帩偮楺恖偑廩枮偟偰偄偨丅戝嶃壞偺恮偱偼丄偦偺楺恖偨偪偵壠峃棪偄傞搶孯偼嬯愴傪嫮偄傜傟偰偄傞丅
丂傑偨丄嶳暁偼愴崙帪戙偵偼僗僷僀偲偟偰傕棙梡偝傟偨丅慜偵婰偟偨傛偆偵丄晲揷怣尯偼嶳暁傪妶梡偡傞戙彏偲偟偰嶳暁偺晛惪栶傪柶彍偟偨偟丄崱愳媊尦偼晉巑懞嶳廋尡傪桪嬾偟偨丅偟偐偟丄嶳暁偵偼媡僗僷僀偺婋尟傕偁偭偨丅
丂壠峃偼偙偺偙偲傕弉抦偟偰偄偨丅偩偐傜丄斵偼挸曬偵嶳暁傪巊傢側偐偭偨丅偐傢傝偵峛夑傗埳夑偺擡幰傪梡偄偨偺偩偭偨丅
丂枊晎偼傑偢嶳暁朄搙傪岞晍偟丄偙傟傑偱斾妑揑帺桼偩偭偨嶳暁偺廆嫵妶摦傪婯惂偟巒傔偨丅
丂偨偲偊偽丄嶳暁朄搙偵偼師偺傛偆側婯掕偑偁傞丅
丂嶳暁偵偲偭偰掕廧偲偼嶳暁惗柦傪扗傢傟傞偙偲傪堄枴偡傞丅嶳暁偑曱擖傝偟丄婋尟傪朻偟偰寖偟偄廋峴傪峴偄丄嶳偺楈婥傪懱尰偟偰偄傞偲恖乆偑怣偠傞偐傜偙偦丄嶳暁偺尡椡偼偦偺埿椡傪敪婗偡傞丅偦傟偑嶳偐傜壓傝偰恖乆偵崿偠偭偰惗妶偟丄戝崻傗枴慩偺戄偟庁傝傪偟偨傝丄枅擔偺垾嶢傪岎傢偡傛偆偵側偭偰偼丄嶳暁偺惗妶傕帺暘偨偪偲帡偨傝傛偭偨傝偩偲尒攋傜傟傞丅
丂堎奅惈偼徚柵偟丄偦傟傑偱恖乆偑嶳暁偵書偄偰偄偨嫲晐怱偲側偄傑偤偵側偭偨怣棅偼幐傢傟偰偟傑偆丅恊偟傒偲嫲晐偲偼椉棫偟側偄傕偺偱偁傞丅嶳暁偑挻擻椡偲偄偆尡椡傪敪婗偱偒傞偺傕丄棦偺恖乆偑嶳暁偑帺暘偨偪偲堎幙偺傕偺偱偁傞偲擣幆偟偰偄傞偙偲偑慜採偱偁傞丅
丂枊晎偺嶳暁婯惂偼嫮壔偺堦搑傪偨偳傞丅嶳暁偺掕廧惌嶔傪寛掕偟偨屻丄枊晎偼慡崙偺嶳暁傪娗棟偝偣傞偨傔偵丄嶳暁惃椡偺捀揰偵偁偭偨嫗搒惞岇堾偺杮嶳攈偲丄摨偠偔嫗搒戠岉帥嶰曮堾偺摉嶳攈偺椉攈偵慡崙偺嶳暁偺彾埇傪柦偠傞丅嶳暁偼昁偢俀偮偺攈偺偳偪傜偐偵懏偡傞偙偲偲偟丄嶳暁偺恖暿挔傕嶌傜傟傞傛偆偵側傞丅
丂杮嶳攈偲摉嶳攈偲偺戝傑偐側堘偄偼丄嶳椦偱偺廋峴偺偝偄孎栰偐傜擖偭偰媑栰偵帄傞偐丄偦偺媡偵媑栰偐傜孎栰偵帄傞偐偲偄偆廋峴僐乕僗偵偁傞偑丄偦偺傛偆側嵎堎偼偙偺偝偄栤戣偵偡傞昁梫偼側偄丅
丂梫偡傞偵丄枊晎偼椉攈偵嶳暁娗棟偺媊柋傪晧傢偣丄偁傢偣偰椉攈娫偺挿擭偵傢偨傞懳棫傪棙梡偟丄椉幰偺峈憟偵偦偺僄僱儖僊乕傪岦偗偝偣傞偙偲偱嶳暁惃椡偺庛懱壔傪慱偭偨偺偩偭偨丅
丂偝傜偵嶳暁偵捛偄懪偪傪偐偗傞傛偆偵丄枊晎偼姲暥俇擭(1666)丄乽彅幮擨媂恄庡朄搙乿傪惂掕偟偨丅偙偺朄搙偙偦媑揷恄摴偵嫮戝側椡傪梌偊丄傕偭偰媑揷恄摴傪偟偰擔杮偺恄摴奅偵孨椪偣偟傔丄偦偺戙彏偵峕屗枊晎偺恄摴惌嶔傪拤幚偵戙曎偝偣偨偺偱偁傞丅
丂姲暥墢婲偼孎栰廋尡宯偺嶳暁偱偁偭偨尃暫塹堦懓偑丄枊晎偺惌嶔偵傛偭偰嶳暁偐傜幮恖偵揮姺偡傞偙偲傪梋媀側偔偝傟偰嶌惉偝傟偨恄榖偱偁傞丅扢宯恾傕偦偺姲暥墢婲偵偲傕側偭偰曇傑傟偨尃暫塹堦懓偺擭戙婰偱偁傞丅
丂偦偟偰摗暫塹偲偺懳棫傪崕暈偟丄偲傕偐偔傕幮恖偵曄恎偟偨尃暫塹堦懓偼尃暫塹偑姶摼偟偨棾捾尃尰傪棾捾嶳忋偵釰傞偙偲偵側偭偨丅
丂偟偐偟丄偦偺棾捾尃尰偑嵞傃媑揷恄摴偵傛偭偰恄奿偺曄峏傪媮傔傜傟偨寢壥丄嶌惉偝傟偨偺偑墑嫕椢婲側偺偱偁傞丅
丂尃暫塹堦懓偼姲暥偐傜墑嫕偺偍傛偦俉侽擭偺娫偵丄擇搙偵傢偨傝媑揷恄摴偲偄偆嫄戝側夦暔偺慜偵旼傪孅偟偨丅
丂傑偨丄偦偺媑揷壠偑恄摴奅偵埿惃傪怳傞偆偙偲偑偱偒偨偺傕丄攚屻偵峕屗枊晎偺恄摴惌嶔偲嶳暁懳嶔偲偑偁偭偨偐傜偩偭偨丅偙傟傜偺枊晎偺惌嶔傕丄傑偨姲暥墢婲偲墑嫕墢婲偵戝偒側塭嬁傪梌偊偨丅
峕屗枊晎偺嶳暁惌嶔
丂傑偢丄峕屗枊晎偺嶳暁懳嶔偵偮偄偰尒傞偙偲偵偡傞丅丂摽愳壠峃偼朙恇壠傪柵傏偟擔杮偺巟攝幰偲側偭偨偺偪丄栴宲偓憗偵奺庬偺朄搙傪惂掕偟偨丅惌帯揑偵偼晲壠彅朄搙傗嬛拞暲岞壠彅朄搙偑嫇偘傜傟傞偑丄暓嫵奅偵懳偟偰傕壠峃偑惗懚拞偐傜師乆偲奺廆偛偲偺朄搙傪惂掕偟丄帥堾婯惂傪奐巒偟偨丅偡側傢偪丄宑挿俈擭偺忩搚廆偵巒傑傝丄偦偺屻丄揤戜廆丄恀尵廆丄憘摯廆丄椪嵪廆側偳偱偁傞丅
丂偙傟傜帥堾朄搙惂掕偺栚揑偼丄帥堾傪廆嫵偺榞偺拞偵墴偝偊崬傒丄惌帯傊岥弌偟偡傞偙偲傪屌偔嬛偠傞偙偲偩偭偨丅婨撪偺戝帥堾偑朙恇曽偲寢傫偱丄斀摽愳惃椡壔偡傞偙偲傪嫲傟偨偐傜偱偁傞丅
丂暯埨帪戙偐傜墑楋帥傗嶰堜帥側偳偺憁暫偑丄悢傪棅傫偱挬掛偵嫮慽偟偨傝丄帪偺惌帯尃椡偵斀峈偡傞偙偲偼捒偟偔側偐偭偨丅枊晎偼帥堾偵偙傟傪嫋偝偢丄尩偟偄懺搙偱朷傓偙偲偵偟偨偺偱偁傞丅
丂忩巑恀廆偺杮婅帥偼愇嶳崌愴傪怐揷怣挿偲屳妏偵愴偭偨丅奺抧偵堦岦堦潉偑惗婲偟丄愴崙帪戙傪偄偭偦偆崿棎偝偣偨丅壠峃帺恎傕崱愳媊尦偺巰偵傛偭偰恖幙偺恎暘偐傜夝曻偝傟偨偑丄壀嶈偵婣忛偟偰娫傕側偔丄壠恇傜傪姫偒崬傫偩堦岦堦潉偵擸傑偝傟偨嬯偄宱尡偑偁傞丅
丂壠峃偼杮婅帥偲偄偆戝柤傪椊偖嫮戝側惃椡傪嶦偖偨傔偵丄偙傟傪搶惣椉杮婅帥偵暘妱偟偨偲偄傢傟偰偄傞丅
丂嶳暁傪懳徾偲偟偨嶳暁朄搙偑敪椷偝傟偨偺偼宑挿侾俉擭(1613)丄偦偟偰偙傟偵娭楢偡傞屼怗彂偺岞晍偼姲暥俀擭(1662)偱偁傞丅偙偺偙傠偐傜枊晎偼嶳暁懳嶔偵杮崢傪擖傟巒傔偨丅枊晎偼嶳暁偑帩偮婋尟傪嶡抦偟偰偄偨丅嶳暁偺帩偮慡崙帺嵼偺婡摦椡傪嫲傟偨丅
丂愄偐傜嶳暁偼曄憰偡傞偵偼奿岲偺巔側偺偩丅尮媊宱偼孼棅挬偺捛媮傪摝傟傞偨傔丄嶳暁偵巔傪曄偊丄曎宑埲壓偺廬幰偨偪偲墱廈偵摝傟偨丅斵傜偺摝朣偵偼孎栰傗媑栰丄搶杒偺塇崟嶳側偳偺嶳暁偺嫤椡偑偁偭偨偲偄傢傟傞丅
丂屆偔偼恜怽偺棎偺偝偄丄戝奀恖峜巕偼嵞婲傪恾傞偨傔丄愽暁偟偰偄偨媑栰偐傜旤擹偵擖偭偨丅偙偺偲偒偺峜巕傕嶳暁巔偩偭偨丅撿杒挬偺憟棎偱偼丄岇椙恊墹偼傗偼傝嶳暁偵曄憰偟偰孎栰偵擖偭偰偄傞丅
丂偙偺傛偆側惌帯斊傗楺恖丄斊嵾幰側偳偑嶳暁巔偱彅崙傪減渏偟丄奺抧偺摨椶偲楢棈傪庢傝崌偆偙偲傪曻抲偟偰偄偰偼丄偄偮枊晎揮暍偺婇偰偵寢傃偮偐側偄偲傕尷傜側偄丅偦偺摉帪丄慡崙偵偼枊晎偵晄枮傪帩偮楺恖偑廩枮偟偰偄偨丅戝嶃壞偺恮偱偼丄偦偺楺恖偨偪偵壠峃棪偄傞搶孯偼嬯愴傪嫮偄傜傟偰偄傞丅
丂傑偨丄嶳暁偼愴崙帪戙偵偼僗僷僀偲偟偰傕棙梡偝傟偨丅慜偵婰偟偨傛偆偵丄晲揷怣尯偼嶳暁傪妶梡偡傞戙彏偲偟偰嶳暁偺晛惪栶傪柶彍偟偨偟丄崱愳媊尦偼晉巑懞嶳廋尡傪桪嬾偟偨丅偟偐偟丄嶳暁偵偼媡僗僷僀偺婋尟傕偁偭偨丅
丂壠峃偼偙偺偙偲傕弉抦偟偰偄偨丅偩偐傜丄斵偼挸曬偵嶳暁傪巊傢側偐偭偨丅偐傢傝偵峛夑傗埳夑偺擡幰傪梡偄偨偺偩偭偨丅
嶳暁傪掕廧偝偣傞
丂怣尯傗媊尦偲堘偄丄嶳暁傪婋尟帇偟偨壠峃偼斵傜偺掕廧惌嶔傪庢傝巒傔傞丅壠峃巰屻偺峕屗枊晎傕偦偺惌嶔傪摜廝偟偨丅丂枊晎偼傑偢嶳暁朄搙傪岞晍偟丄偙傟傑偱斾妑揑帺桼偩偭偨嶳暁偺廆嫵妶摦傪婯惂偟巒傔偨丅
丂偨偲偊偽丄嶳暁朄搙偵偼師偺傛偆側婯掕偑偁傞丅
僀
儘
僴
僯
儘
僴
僯
嵳楃朄帠偼寉偔偣傛
柉壠傪庁傝丄暓抎傗娕斅傪弌偟偰偼側傜側偄
朄堖憰懇偼寢峔側傕偺偵偟偰偼側傜側偄
暓傗栶峴幰側偳偺奊憸傪妡偗偰丄恖乆偺婩擮偺媮傔偵墳偠偰傕傛偄偑丄婩擮偑廔傢偭偨傜偡偖曅晅偗傛
柉壠傪庁傝丄暓抎傗娕斅傪弌偟偰偼側傜側偄
朄堖憰懇偼寢峔側傕偺偵偟偰偼側傜側偄
暓傗栶峴幰側偳偺奊憸傪妡偗偰丄恖乆偺婩擮偺媮傔偵墳偠偰傕傛偄偑丄婩擮偑廔傢偭偨傜偡偖曅晅偗傛
丂偙偙偵偁傞婯掕偺悢乆偼丄偙傟傑偱嶳暁偑帺桼偵嶳偐傜棦偵壓傝丄棦恖偵巤偟偰偄偨婩摌傗嵳楃偵朄偺栐傪偐傇偣傛偆偲偡傞傕偺偱偁傞丅
丂偮偄偱枊晎偼姲暥俀擭偺屼怗彂偱丄嶳暁偺嫃廧偺帺桼傪扗偭偰偟傑偭偨丅丂嶳暁偵偲偭偰掕廧偲偼嶳暁惗柦傪扗傢傟傞偙偲傪堄枴偡傞丅嶳暁偑曱擖傝偟丄婋尟傪朻偟偰寖偟偄廋峴傪峴偄丄嶳偺楈婥傪懱尰偟偰偄傞偲恖乆偑怣偠傞偐傜偙偦丄嶳暁偺尡椡偼偦偺埿椡傪敪婗偡傞丅偦傟偑嶳偐傜壓傝偰恖乆偵崿偠偭偰惗妶偟丄戝崻傗枴慩偺戄偟庁傝傪偟偨傝丄枅擔偺垾嶢傪岎傢偡傛偆偵側偭偰偼丄嶳暁偺惗妶傕帺暘偨偪偲帡偨傝傛偭偨傝偩偲尒攋傜傟傞丅
丂堎奅惈偼徚柵偟丄偦傟傑偱恖乆偑嶳暁偵書偄偰偄偨嫲晐怱偲側偄傑偤偵側偭偨怣棅偼幐傢傟偰偟傑偆丅恊偟傒偲嫲晐偲偼椉棫偟側偄傕偺偱偁傞丅嶳暁偑挻擻椡偲偄偆尡椡傪敪婗偱偒傞偺傕丄棦偺恖乆偑嶳暁偑帺暘偨偪偲堎幙偺傕偺偱偁傞偲擣幆偟偰偄傞偙偲偑慜採偱偁傞丅
丂枊晎偺嶳暁婯惂偼嫮壔偺堦搑傪偨偳傞丅嶳暁偺掕廧惌嶔傪寛掕偟偨屻丄枊晎偼慡崙偺嶳暁傪娗棟偝偣傞偨傔偵丄嶳暁惃椡偺捀揰偵偁偭偨嫗搒惞岇堾偺杮嶳攈偲丄摨偠偔嫗搒戠岉帥嶰曮堾偺摉嶳攈偺椉攈偵慡崙偺嶳暁偺彾埇傪柦偠傞丅嶳暁偼昁偢俀偮偺攈偺偳偪傜偐偵懏偡傞偙偲偲偟丄嶳暁偺恖暿挔傕嶌傜傟傞傛偆偵側傞丅
丂杮嶳攈偲摉嶳攈偲偺戝傑偐側堘偄偼丄嶳椦偱偺廋峴偺偝偄孎栰偐傜擖偭偰媑栰偵帄傞偐丄偦偺媡偵媑栰偐傜孎栰偵帄傞偐偲偄偆廋峴僐乕僗偵偁傞偑丄偦偺傛偆側嵎堎偼偙偺偝偄栤戣偵偡傞昁梫偼側偄丅
丂梫偡傞偵丄枊晎偼椉攈偵嶳暁娗棟偺媊柋傪晧傢偣丄偁傢偣偰椉攈娫偺挿擭偵傢偨傞懳棫傪棙梡偟丄椉幰偺峈憟偵偦偺僄僱儖僊乕傪岦偗偝偣傞偙偲偱嶳暁惃椡偺庛懱壔傪慱偭偨偺偩偭偨丅
丂偝傜偵嶳暁偵捛偄懪偪傪偐偗傞傛偆偵丄枊晎偼姲暥俇擭(1666)丄乽彅幮擨媂恄庡朄搙乿傪惂掕偟偨丅偙偺朄搙偙偦媑揷恄摴偵嫮戝側椡傪梌偊丄傕偭偰媑揷恄摴傪偟偰擔杮偺恄摴奅偵孨椪偣偟傔丄偦偺戙彏偵峕屗枊晎偺恄摴惌嶔傪拤幚偵戙曎偝偣偨偺偱偁傞丅
恄摴奅偵埿惃傪怳傞偭偨媑揷恄摴偲偼
僇僱僩儌
僂儔儀
丂媑揷恄摴偼墳恗偺棎偺偙傠丄媑揷寭丂嬩偑彞偊偨恄摴偱偁傞丅媑揷壠偼傕偲僩晹壠偲偄偄丄屆戙偐傜僩愯傗妛栤偺壠嬝偩偭偨丅
丂寭嬩偼帺壠偵揱傢傞壠妛傪婎慴偲偟丄偙傟偵暓嫵丄堿梲摴丄摴嫵側偳庢傝擖傟丄擔杮彂婭恄戙姫偺島媊傗乽拞丂恇丂釶乿偺拲庍傪峴偄丄媑揷壠偺恄摴傪妋棫偟偨丅偙偺帪戙偵偼棩椷惂壓偺恄媉攲敀愳恄摴傕偁偭偨丅偟偐偟丄媑揷恄摴偼偙傟傪椊夗偟擔杮嵟戝偺恄摴壠偲側偭偨丅
丂偦偺嫵愢偼乽愭戙媽帠杮婭乿乽擔杮彂婭乿乽屆帠婰乿偺嶰晹偺彂傪婎杮惞揟偲偟丄偲偔偵偦傟偧傟偺恄戙姫偵媑揷恄摴偺惛悜偑梋偡偲偙傠側偔帵偝傟偰偄傞偲庡挘偡傞丅
丂寭嬩偺恄摴偼桞堦恄摴偲徧偝傟偨丅偦偺柤徧偵丄寭嬩偺恄摴奅傪偍偺傟偺恄摴偱摑堦偟傛偆偲偄偆栰怱偲帺晧偑偙傔傜傟偰偄傞丅
丂偦偟偰丄偙偺嶰晹偺屆揟偵搊応偡傞恄偺拞偐傜丄崙丂忢丂棫丂柦偑愨懳尨弶偺恄偲偟偰慖戰偝傟丄寭嬩偑嫗搒媑揷嶳偵寶愝偟偨嫄戝側敧妏宍偺戝尦媨偵姪惪偝傟偨丅戝尦媨傪拞墰偵抲偒丄偦偺廃埻偵偼敧恄揳丄墑婌幃撪幮嶰愮梋幮傪攝抲偟偨丅
丂偙偺戝尦媨偵偁傠偆偙偲偐丄埳惃恄媨偺恄楈偱偁傞傾儅僥儔僗戝恄偑旘傃堏偭偨偲斵偼庡挘偟偨偺偱偁傞丅帪偺揤峜偵偙傟傪枾捄偝偊傕偟偨丅斵偼戝尦媨傪埳惃恄媨傛傝傕嫮戝側恄偺崙偲偡傋偔丄惌帯揑偵夋嶔偟偨偺偱偁傞丅
丂斵偼傒偢偐傜偺壠宯偺恄媉奅偵偍偗傞惓摑惈傪悽偵愰揱偡傞偨傔丄屆戙偐傜恄媉傪巌偭偰偄偨拞恇巵偺宯恾傪僩晹巵偺拞偵庢傝崬傫偩丅偙偺傛偆側側傝傆傝峔傢偸庤抜傪庢偭偰丄媑揷恄摴偼恄摴奅偺捀揰偵棫偭偨丅
丂寭嬩偼乽嶰嫵偺堦揌傕彟傔偢乿偲丄媑揷恄摴偑暓嫵傗摴嫵側偳偺塭嬁傪傑偭偨偔庴偗偰偄側偄偲偟丄偦偺撈帺惈傪嫮挷偟偨丅偟偐偟丄幚嵺偵偼恀尵枾嫵傗堿梲摴偺嫵媊傪庢傝擖傟偰帺壠偺恄摴傪峔惉偟偰偄偨丅
丂斵偑婎慴傪抸偄偨媑揷壠偺恄摴偼丄幒挰帪戙偵偼愴崙戝柤偺斴岇傪摼偨丅愴崙晲彨偑愴憟偺彑棙傪恄暓偵婩傝丄庺弍偵傛偭偰彑棙偺梊尵傪摼偰偄偨偙偲偼丄僲僲乕偺偲偙傠偱尒偨偲偍傝偱偁傞丅
丂峕屗帪戙偵偼媑揷壠偼尃杁弍悢偵挿偗偨媑揷寭尒偑峕屗枊晎偵愙嬤偟丄枊晎偺嫮椡側巟帩傪摼偨丅寭尒偼偦傟埲慜偵傕怐揷怣挿傗朙恇廏媑偵庢傝擖偭偰偄偨丅偦偟偰媑揷壠偼乽恄摴挿忋乿乽恄媉娗椞挿忋乿傪橤徧偡傞丅
丂枊晎偼媑揷壠傪棙梡偟偰恄摴奅傪摑惂偟傛偆偲偟丄偦偺媑揷壠偼枊晎偐傜乽彅幮擨媂恄庡朄搙乿傪梌偊傜傟偰丄枊晎偺恄摴惌嶔偺庤愭偲側偭偨丅
丂暓嫵奅偵懳偟偰偼丄枊晎偼奺廆攈偵怗摢傪抲偐偣偰丄朄椷偦偺懠偺捠払帠崁偺揙掙傪恾偭偨丅摨偠傛偆偵丄恄摴奅偱偼媑揷壠偑掕傔傞恄幮偑怗摢偲側傝丄枊晎偺巜椷偑慡崙偺恄幮偵偔傑側偔峴偒搉傞傛偆偵側傞丅
丂壛偊偰彅幮擨媂恄庡朄搙偼丄姱埵偺側偄幮恖偼昁偢敀挘偺傒傪拝梡偡傞傕偺偲偟丄庪堖傗塆朮巕側偳偺拝梡偵偼媑揷壠偺嫋偟忬丄偄傢備傞恄摴嵸嫋忬傪梫偡傞偲婯掕偟偨丅屻偵偼偙偺婯掕偵堘斀偟丄嵸嫋忬偺岎晅傪庴偗偢偵憰懇傪拝梡偟偨応崌偺庢傝掲傑傝傕嫮壔偝傟偨丅
丂敀挘偲偼敀晍偺昞棤偵屝傪嫮偔傂偄偰巇棫偰偨偩偗偺庪堖偱丄婱懓偺廬幰傗壓恖偺憰懇偱偁傞丅
丂庪堖偼寴抧偵暥條傪埢栚偵尰偟偨搤梡偲丄幯抧偵巺傪婑偣偰暥條傪弌偟偨壞梡偑偁傞丅側偍偦偺暥條偵偼棫桹傗徏旽丄孮愮捁側偳崑壺側柾條偑怐傝弌偝傟丄巋廕傕偁傞丅
丂廆嫵偵偼憫尩偑昁梫偱偁傞丅幮恖偑壓杔偺拝偡傞敀挘偱恄偵廽帉傪曺偘偨傝丄鈹傪峔偊偰傕埿尩偼敽傢側偄丅傗偼傝幮恖偑塆朮巕偵庪堖傪拝梡偟丄庤偵鈹傪帩偪丄懌偵偼崟偄愺孊傪棜偒丄恄偵巇偊傞廳乆偟偄巔傪恖乆偵屩帵偡傞偐傜偙偦恄偺埿岝傕曐偨傟傞丅敀挘偱恄帠傪峴偊偲偄偆偙偲偼丄幮恖傪攑嬈偣傛偲偄偆偵摍偟偄丅
丂枊晎偺昡掕強偺埖偄傕庪堖偐敀挘偐偱埖偄偑堎側偭偰偄偨丅庪堖帒奿幰偼昡掕強偺墢偺忋偵拝嵗偱偒偨偑丄敀挘偼墢偵偼忋偑傟側偐偭偨丅摉慠丄枊晎偺嵸寛傕庪堖偵桳棙側傕偺偲側傞丅
丂偦傟偽偐傝偱偼側偄丅媑揷壠偼幮恖偨偪偵暯埨帪戙偺巵偱偁傞尮巵傗摗尨巵側偳傪柤忔傜偣丄壛偊偰榓愹庣丄愛捗庣偲偄偭偨庴椞柤傗敼恖惓丄媨撪彮曘丄媨撪彆側偳偺彅姱怑柤傪梌偊偨丅悽忋偱偼偙傟傪媑揷姱偲偄偭偨(側偍丄屆崱漭婰榐側偳傪彂偄偨暯嶳戧巵偺挿栧惓偺偙偲偩偑丄乽挿栧惓乿偲偄偆姱柤偼側偄丅偟偨偑偭偰乽挿栧惓乿偺柤偼丄惓妋偵偼乽挿栧庣乿偲偁傞傋偒偱偁傞丅偦傟傪乽挿栧惓乿偲偟偨偺偼丄廃杊偲挿栧傪巟攝偟偰偄偨栄棙斔偺挿栧庣偵墦椂偟偨偺偱偼側偐傠偆偐丅側偍偙傟偼搶戝巎椏曇嶽強偺嫶杮愭惗偵偛嫵帵傪偄偨偩偄偨)丅
丂偙傟傜偺姱怑偵偼偡偱偵偦偺惗柦傪幐偭偨棩椷惂偺屲埵丄榋埵偲偄偆姱埵偑偲傕側偭偨丅宍幃偺傒偺尃埿偱偁傞丅傕偪傠傫丄偙傟傜偼桳椏偱梌偊傜傟偨傕偺偩偭偨丅 丂師偺傛偆側帋嶼偑偁傞丅偁傞懞偺巵恄偺幮恖偺椺偱偁傞丅恄摴嵸嫋忬傪庼梌偝傟傞偨傔偵偼丄忋嫗偟偰媑揷恄摴偺摿孭傪庴偗側偗傟偽側傜側偄丅偦偺岎捠旓丄懾嵼旓丄庴椞柤傗姱埵傪摼傞旓梡偼丄偟傔偰侾俆椉偲偄偆丅
丂傑偨丄彑庤偵幮恖偵側傞傢偗偵偼備偐側偄丅偦偺恄幮傪巟攝偡傞斔庡偺悇慐忬傕昁梫偩偭偨丅偦偺幱楃傕偟側偗傟偽側傜側偄丅
丂惏傟偰恄姱偱偁傞偙偲傪媑揷壠偐傜嫋壜偝傟傟偽丄懞偺庡偩偭偨柤庡傗巵巕傪廤傔偰斺業偺墐傕奐偔丅
丂偄傑丄嬥堦椉傪幍枩墌側偄偟幍枩屲愮墌偲偡傞偲丄廫屲椉偼昐廫悢枩墌偲側傞丅偙傟偵忋偵婰偟偨傛偆側嶨懡側旓梡傪壛偊傞偲丄擇昐枩墌偐傜嶰昐枩墌傪梫偟偨偲偄偆丅拞彫偺幮恖偵偲偭偰偼夁戝側晧扴偱偁傞丅
丂偩偐傜懞偵傛偭偰偼丄懞恖偨偪偑崌椡偟偰傢偢偐偱偼偁偭偰傕镾暿偺宍偱丄憤妟堦椉埲忋偺嬥妟傪朢偟偄懞擖梡偱晧扴偟偰偄傞椺傕偁傞丅懞偵偲偭偰傕巵恄偺偙偲偲偼偄偊丄弌旓偑戝偒偄偲堿偱嬸抯傪偙傏偡幰傕偄偨傜偟偄丅
丂偦偺傎偐丄偄偔偮偐偺椺傪嫇偘傞偲丄恄幮崋傪嫋壜偝傟傞偺偵妟帤偲傕偱廫椉(栺俈侽枩墌)丄嵶偐偄偲偙傠偱偼塆朮巕拝梡偵嬥堦暘(栺侾枩俉愮墌)丄妡弿傗孊偺巊梡嫋壜偵傕偦傟偧傟嬥堦暘偑昁梫偩偭偨丅媑揷壠偵偼偙偺傛偆側奺暔昳偺壙奿傗嫋壜偵懳偡傞楃嬥偺儕僗僩偑嶌傜傟偰偄偨丅
丂媑尨戧巵偺巕懛偺偍戭偵偼丄暥壔俀擭(1805)偺傕偺偱偼偁傞偑丄嶰庬懢釶傪媑揷壠偐傜嫋偝傟偨偙偲傪帵偡彂椶偑巆傞丅
丂恄姱偼暥帤偳偍傝摢偺偰偭傌傫偐傜偮傑愭傑偱媑揷壠偵娗棟偝傟偰偄偨偙偲偵側傞丅
丂抧曽偺堦彫幮偵夁偓側偄棾捾尃尰偵傕媑揷壠偺埑椡偼妋幚偵壛偊傜傟偰偄偨丅偙傟傪帵偡傛偆側婰帠偑屆崱漭婰榐偵傕偄偔偮偐尒傜傟傞丅偦傟傪擇丄嶰徯夘偡傞丅
丂壝塱俀擭偺偙偲偩偑丄媑揷壠偐傜俀恖偺屼幏栶(媑揷壠偱抧曽恄幮傪娗棟偡傞幚柋扴摉幰)偑桼斾廻偵弌挘偟偰偒偨丅
丂偦偟偰俀恖偼埩尨孲壓偺幮恖慡堳傪椃廻偵屇傃弌偟丄斵傜偐傜偄偪偄偪恄幮偺宱塩忬嫷傪恞偹丄偐偮俀恖偐傜偼媑揷壠偺嵟嬤偺摦偒傗惌嶔側偳傪揱偊偰偄傞丅
丂俀恖偼桼斾廻偵廻攽偟偰偄傞偐傜丄偦傟側傝偺嫙墳偑側偝傟偨偙偲偼偄偆傑偱傕側偄丅
丂傑偨摨偠偙傠丄媑揷壠偺拕抝偑尦暈偟偨偺偱丄偦偺廽媀傪廤傔傞傋偔埩尨孲壓偺幮恖偵怗傟暥偑夢偭偨丅孲壓偺幮恖俀侽恖偑嫽捗偺幮恖戭偱夛崌傪奐偄偰偁傟偙傟嫤媍偺寢壥丄侾恖偁偨傝昐旸(堦旸廫暥偲偟偰堦娧暥)傪廤嬥偟偰偄傞丅偙傟偲偼暿偵廽媀傪帩嶲偡傞戙昞幰偺嫗搒墲暅偺椃旓側偳傕暘扴偟偰偄傞丅
丂偙偺傎偐慜偵傕婰偟偨傛偆偵丄幮恖偑戙懼傢傝傪偡傞偨傃偵嫗搒偵晪偄偰媑揷壠偱摿暿偺嫵堢傪庴偗偰偄傞丅漭婰榐偵傕戝榓庣惓掕偼偠傔埳惃庣惓岲丄戝榓庣惓師側偳暯嶳戧巵偺楌戙幮恖偺忋嫗婰帠偑偁傞偐傜丄傎偐偺扢朷寧巵傗晍戲戧巵側偳偺幮恖偨偪傕摨條偩偭偨偼偢偱偁傞丅
丂傑偨丄挿栧惓帺恎傕漭婰榐偺拞偵斵帺恎偑媑揷壠偐傜岎晅偝傟偨恄摴嵸嫋忬偺杮暥傪昅幨偟偰偄傞丅
丂媑揷壠偼偙偆偟偰峕屗枊晎偺尃埿傪屻弬偵恄埵偲恄崋偺庼梌尃傪撈愯偟丄偁傢偣偰恄姱偺曗擟尃傪庤拞偵擺傔丄嫮椡側恄怑摑惂傪幚巤偟偨丅偦偟偰慡崙偺幮恖傪嬥慘偲惂搙偺椉柺偐傜掲傔晅偗偨偺偱偁偭偨丅
丂枊晎偼帥堾偵憭媀傗暓帠傪攠夘偲偟偰擾柉偲帥抎娭學傪寢偽偣丄廆巪恖暿挔偺嶌惉傪帥堾偵柦偠偨丅偦偺憭媀傕帥堾偺傒偵嫋偟偨丅暓嫵傪帥堾偵撈愯偣偟傔偨丅偦偺寢壥丄嶳暁偼暓嫵偐傜掲傔弌偝傟傞偙偲偵側傞丅
丂懠曽丄嶳暁偑幮恖偵側傠偆偲偟偰傕丄媑揷恄摴偵傛偭偰恄怑偼尩廳偵摑惂偝傟偰偄傞丅偦偺媑揷恄摴偼慡崙偺恄幮偺娗棟尃傪暓嫵帥堾偐傜扗偭偰丄恄怑偵梌偊傛偆偲偡傞丅
丂偦偟偰丄摉慠偺偙偲偱偁傞偑丄暓嫵懁偑偄偆杮抧悅鐟愢傗恄暓廗崌傪斲掕偡傞丅杮抧悅鐟愢偑偁傞偑屘偵丄恄摴偼暓嫵偺壓晽傪庴偗丄憁椀偑暿摉側偳偺抧埵偵偁偭偰丄恄幮偵曭巇偡傞幮恖傪妠巊偟偰偄傞丄偲偄偆偺偑媑揷壠懁偺尵偄暘偱偁傞丅暓嫵懁偼暓偑庡偱恄偑廬丄偄傢備傞暓杮恄鐟偱偁傞丅
丂媑揷恄摴偼偙傟偑娕夁偱偒側偐偭偨丅桞堦恄摴偺柤偺偲偍傝丄恄摴傪暓嫵傛傝桪埵偵抲偔偙偲偑媑揷恄摴偺暓嫵懳嶔偩偭偨偺偱偁傞丅偙偪傜偼恄偑庡丄暓偑廬偺恄杮暓鐟偱偁傞丅
丂幚慔廆嫵偲偟偰丄嫵媊傕枮懌偵帩偨側偄廋尡摴偺嫆傝強偼恄暓廗崌偱偁傞丅(廋尡摴偑偦偺嫵棟傪棟榑壔偟偰丄乽栘梩堖乿乽摜塤榐帠乿偼偠傔丄奺庬偺嫵媊彂傪曇傓傛偆偵側傞偺偼峕屗帪戙屻婜偱偁傞丅偄偄偐偊傟偽丄廋尡摴偑悐戅偟偨屻偵丄偙偺傛偆側懱宯揑側彂暔偑惉棫偟偨偺偱偁傞丅廋尡摴偑枊晎偐傜婯惂傪庴偗丄幚慔柺偑戝偒偔惂尷偝傟偨偨傔偵丄壣偑偱偒偨偺偩)丅廋尡摴偵偁偭偰偼乽恄偐暓偐乿偲偄偆娤擮偼側偄丅偁傞偺偼乽恄傕暓傕乿偱偁傞丅偦傟偑摉帪偺弾柉偺姶妎偱傕偁偭偨丅弾柉偵偲偭偰偼乽恄偐暓偐乿傛傝傕屼棙塿偺桳柍偱偁傞丅尰悽棙塿偱偁傞丅嶳暁偼偦偺弾柉偺梸媮偵摎偊傞廆嫵幰偩偭偨丅
丂偲偙傠偑媑揷恄摴偼廋尡摴傪斲掕偟丄恄傪桪埵偵抲偔丅懠曽偱暓嫵偼暓傪桪愭偡傞丅暓嫵偲媑揷恄摴偺娫偵偁偭偰嶳暁偼丄椉幰偐傜抏偒弌偝傟偰偟傑偭偨偺偱偁傞丅
丂嶳暁偼媑揷恄摴偺巟攝壓偵擖偭偰幮恖偲側傞偐丄恀尵廆傗揤戜廆偵夵廆偟偰憁椀偵側傞偐偟偐側偔側偭偨丅傕偟俀偮偲傕嫅斲偡傟偽丄嶳暁偼偨偩偺柉娫偺攓傒壆偵懧偡傞丅堦夘偺婩摌巘偵棊偪傇傟傞偺偱偁傞丅屩傝崅偄嶳暁偵偼懴偊傜傟傞偙偲偱偼側偐偭偨丅
丂偵傕偐偐傢傜偢丄恄暓偳偪傜偵傕梌偡傞偙偲偑偱偒側偄傑傑偵棊楫偟偰偄偭偨嶳暁偼懡偐偭偨偼偢偩丅堜尨惣掃偺彫愢偵傕乽巇妡偗嶳暁乿偺柤偱偵偣嶳暁偑搊応偡傞丅岇杸抎偵嵶岺傪巤偟丄嵓媆傑偑偄偺婩摌傪偟偰偄偨丅尦椢偺崰偵偼偙偺傛偆側夦偟偄嶳暁偑墶峴偟偰偄偨丅偦偟偰斵傜偑偝傜偵棊偪傇傟傞偲丄嵳暥岅傝傪偼偠傔丄偪傚傫偑傟傗垻曫懮梾宱側偳偺寍擻偵傛偭偰丄栧晅偗傪偟側偑傜奺抧傪夢傝丄嵶乆偲惗妶傪棫偰傞傛偆偵側傞偙偲偼擔杮寍擻巎偺婰偡偲偙傠偱偁傞丅
丂枊晎偑嶳暁偺婯惂傪嫮壔偟丄媑揷恄摴偑恄摴奅傪巟攝偟巒傔偨姲暥偲偄偆帪婜偵丄尃暫塹偲摗暫塹偼棾捾尃尰偐晉巑懞嶳廋尡偐偱憟偭偨偺偱偁傞丅
丂寢壥偼尃暫塹攈偺彑棙偲側傝丄姲暥墢婲偲扢宯恾偑嶌惉偝傟丄尃暫塹偑斵偵忔傝堏偭偨棾捾尃尰偺幮恖偱偁傞偙偲傪晍戲懞傗暯嶳懞丄崟愳懞側偳抧尦偺懞恖偨偪偵彸擣偝傟偨丅攕傟偨摗暫塹偼捛曻偝傟偰晉巑嶳榌偵嫀偭偰峴偭偨丅
丂尃暫塹偼嶳暁偐傜幮恖偵曄恎偡傞偙偲偵偲傕偐偔傕惉岟偟偨偺偱偁傞丅怘偄媗傔偨嶳暁偲偟偰丄恖乆偐傜層嶶廘偄栚偱尒傜傟偨傝丄寉曁偝傟偢偵偡傫偩偺偩偭偨丅
丂偦偟偰尃暫塹偲斵偺堦攈偼丄棾捾嶳忋偵彫偝偄側偑傜傕弜壨偵偍偗傞孎栰椉強尃尰偺揱摑傪庴偗宲偄偱丄棾捾尃尰偺幮傪寶偰傞偙偲偑偱偒偨丅偦傟偑尰嵼傕巆傞墱偺堾側偺偱偁傞丅偦偺墱偺堾偺娾偼椉強尃尰偑偼偠傔偰孎栰偵崀傝偨偲揱偊傞僑僩價僉娾偵尒棫偰偨傕偺偱偁傞丅
丂宑挿侾俀擭(1607)偺暥彂偵偁傞傛偆偵乽偙偺嶳偼揤嬬偺偡傒偐偩偐傜丄旕忢偵峳傟偰偄偰丄堦棦巐曽偵擖偭偰棃傞幰偼偄側偄乿偲偄偆偺偼丄斵傜偑忋偭偨棾捾嶳偺摉帪偺忬嫷傪尰偟偰偄傞偲偄偊傛偆丅孎栰嶰嶳偺惃椡偑丄弜墦椉崙偐傜揚戅傪梋媀側偔偝傟偨偁偲丄恖傕擖傜偢峳傟曻戣偵側偭偰偄偨偺偱偁傞丅
丂傑偨丄屼杮幮憿塩擵妎挔偼丄尃暫塹揱愢傪婰偟偰偐傜丄乽媨拰棫偰乿偁傞偄偼乽媨拰懢晘偔棫偰乿偲彂偄偰偄傞丅乽懢晘偔乿偼暥忺偲偟偰傕丄弶傔偰棾捾尃尰偺彫幮傪寶偰偨帠忣傪暔岅傞傕偺偱偁傞丅
丂棾捾嶳偼奀敳愮嘼傪墇偊傞丅寛偟偰廧傓偺偵堈偟偔側偄丅嫃廧偺帺桼傪扗傢傟丄棾捾尃尰偺幮恖偲偟偰惗偒傞偨傔偵偼丄搤偺姦偝偺尩偟偄棾捾嶳拞偱曢傜偝偞傞傪摼側偄丅偟偐偟丄偳傫側偵昻偲姦偵嬯偟傕偆偲傕丄姲暥墢婲偵偁傞傛偆偵尃暫塹偨偪偼棾捾尃尰偺戸愰偵廬偭偰丄偙偺恄偵曭巇偟側偗傟偽側傜側偐偭偨偺偱偁傞丅 丂偦傟偽偐傝偱偼側偄丅棾捾尃尰傪巟偊傞傋偒晍戲懞丄扢懞丄暯嶳懞側偳傕昻偟偐偭偨丅偄傑暯嶳傪椺偵庢傠偆丅
丂暯嶳偱偼峕屗帪戙丄侾擭傪捠偠偰暷傪怘傋傜傟偨壠偼丄傢偢偐俀尙偩偭偨偲偄偆丅偦偺摉帪丄暯嶳偺悽懷悢偼栺俆侽偐傜俇侽尙丅偦偟偰丄師偺傛偆側榖偑揱傢傞丅
丂傑偩丄戧巵堦懓偑棾捾嶳拞偵廧傫偱偄偨崰丄暷傪攦偆偨傔偵堦懓偺幰偑偲偒偳偒壓嶳偡傞偙偲偑偁傞丅幮偐傜傕偭偲傕嬤偄暯嶳偵偼暷偑側偄丅傗傓傪摼偢丄幮恖偺壠懓偼昐惄偐傜庁傝偨栰椙拝偵拝懼偊丄幮恖偱偁傞偙偲傪塀偟偰丄暷傪媮傔偰棦偵壓偭偰偄偭偨偲偄偆丅
丂師偺傛偆側榖傕偁傞丅
丂棾捾嶳偐傜朷寧巵丄戧巵堦懓偑傢偐傟偰扢丄媑尨丄暯嶳側偳偵嶶偭偨偲偒丄暯嶳偵壓傝傞戧巵偵暯嶳偺懞恖偼忦審傪晅偗偨丅
丂偦偺忦審偲偼暯嶳偱偼偲偰傕戧巵傪庴偗擖傟傞偩偗偺宱嵪揑側梋桾偑側偄丅偩偐傜丄暯嶳傊偺堏廧偼擣傔傞偑丄懞恖偑埶棅偡傞婩摌傗塽昦棳偟偼偡傋偰柍椏偵偣傛偲偄偆傕偺偩偭偨丅
丂戧巵偼暯嶳懞柉偺梫媮傪庴偗擖傟偨丅埲屻丄楌戙偺幮恖偨偪偼挿旜愳偺乽憲傝恄偺暎乿(偙偺暎偼暯嶳懞偲椬懞偺挿旜懞偲偺嫬奅偵嬤偄)偱塽昦棳偟傗奞拵憲傝傪峴側偭偰偒偨丅
丂偙偺傛偆側榖偑惗傑傟傞偙偲偼丄暯嶳偼傕偪傠傫偺偙偲丄棾捾嶳拞偺崲擄傪嬌傔偨惗妶傪暔岅傞傕偺側偺偩丅
丂尃暫塹偼偠傔朷寧巵傗戧巵偼偙偆偟偨尩偟偄娐嫬偺拞偱丄棾捾尃尰偺幮恖偲偟偰偺戞堦曕傪摜傒弌偟偨偺偱偁傞丅
丂偲偙傠偱丄塽昦棳偟偱偁傞偑丄堛妛偺敪払偟偰偄側偄摉帪丄傂偲偨傃棳峴傝昦偑敪惗偡傟偽丄堦懞慡柵偺嫲傟偡傜偁偭偨丅塽昦棳偟偺偲偒偼丄懞拞偺恖乆偼壠乆偺尙愭偵傓偟傠傪晘偄偰偦偺忋偵惓嵗偟丄恀寱側昞忣偱乽憲傝恄偺暎乿偵岦偐偆幮恖偺偍釶偄傪庴偗丄偦偟偰丄懞偺彲壆埲壓嶰栶偑幮恖偵偮偒廬偭偰偄偨偲偄偆丅
丂帪戙偑壓偑傞偵偮傟偰丄枊晎偲媑揷恄摴偺嶳暁晻偠崬傔偲傕偄偊傞惌嶔偑傑偡傑偡嫮峝側傕偺偲側偭偰備偔丅
丂媑揷恄摴偼棾捾尃尰偵恄奿偺曄峏傪媮傔偰偒偨偺偱偁傞丅
丂媑揷恄摴偺崻杮惞揟偲偄偆傋偒彂暔偼乽愭戙媽帠杮婭乿乽擔杮彂婭乿乽屆帠婰乿偺嶰彂偱偁傞偙偲偼慜偵傕怗傟偨丅偙偺嶰晹彂偵偼揤屼拞庡恄偐傜巒傑傝丄敧昐枩偺恄乆偲屇偽傟傞傛偆偵幚偵懡偔偺恄乆偑婰嵹偝傟偰偄傞丅
丂偲偙傠偑丄懞偺峀応偺曅嬿傗嶳摴偺朤傜傗嫄栘偺崻尦側偳偵偼丄恄摴嶰晹彂偵搊応偟側偄嶨懡側恄偑釰傜傟偰偄偨丅崱擔偱傕悢偼彮側偔側偭偨偲偄偆傕偺偺丄嶳懞傗擾懞偵偼柤傕抦傟偸恄傪釰偭偨釱偲偟偐屇傃傛偆傕側偄彫偝側幮偑偁傞丅
丂偙偺傛偆側彫偝側恄乆偼丄偦傟傪怣偢傞恖偨偪偺捈愙偱擔忢揑側婩傝偺懳徾偵側傞恄乆偩偐傜丄柤慜側偳偼偳偆偱傕傛偐偭偨丅偳偆偱傕傛偐偭偨偲偼尵偄夁偓偩偑丄偦傟傎偳娭怱傪帩偨側偐偭偨丅帺暘偨偪偺擸傒偵偨偩偪偵墳偠丄偦傟傪夝寛偟偰偔傟傞恄偱偁傝偝偊偡傟偽傛偐偭偨偺偱偁傞丅昦婥傗夦変偺偡傒傗偐側姰帯丄暔偺夦偺戅嶶丄奞拵嬱彍丄杺彍偗丄奜晹偐傜怤擖偡傞嵭偄傪杊偖丄側偳側偳偱偁傞丅偩偐傜丄偛恄懱偼幹偩偭偨傝丄屜偩偭偨傝偡傞偙偲傕偁傞丅彫愇偺傛偆側椺傕懡偄丅
丂姍憅帪戙偵忩搚恀廆傪奐偄偨恊阛偼丄愢朄傪暦偒偵棃偨榁庒抝彈偵恄媉晄攓傪孞傝曉偟愢偄偨丅
丂垻栱懮擛棃傪怣怱偡傟偽壗傕嫲傠偟偄傕偺偼側偄丄恄偵棅傞側偲偄偆偺偑斵偺庡挘偩偭偨丅栱懮偺帨斶傪変偑恎偵偄偨偩偗偽丄傕偭偲傕嫲傞傋偒巰傪傕嫲傟傞傕偺偱偼側偄偲孞傝曉偟偨丅偟偐偟丄恖乆偼垻栱懮擛棃偺傎偐偵恄傪怣偠傞偙偲傪傗傔側偐偭偨丅
丂嵟屻偵偼恊阛偺傎偆偑崻晧偗偟偰丄擮暓傪彞偊傞幰偵偼恄偺壛岇偑偁傞偲偄傢偞傞傪摼側偐偭偨丅弾柉偑柤傕側偄恄乆偵婑偣傞嶨懡側怣嬄偵偼崻嫮偄傕偺偑偁偭偨偺偱偁傞丅
丂偟偐偟側偑傜丄擔杮彂婭偺憇戝側恄偺懱宯偵慻傒崬傑傟偨桼弿惓偟偄恄乆偱偼丄恖乆偺偝傑偞傑側婅偄偵偼懄嵗偵懳墳偱偒側偄丅恄乆偑慻怐壔偝傟丄暘嬈壔偟偰偄傞偐傜丄懡悢偺恖乆偺帩偮偄傠偄傠側梫朷偵偼晀懍偵墳偠偒傟側偄偺偩丅
丂偲偙傠偑丄媑揷恄摴偼偙偺傛偆側恖乆偺慺杙側恄怣怱偺幚懺傪柍帇偟丄恄幮偵懳偟偰嶰晹彂偺恄乆埲奜偺恄傪擣傔側偔側偭偨偺偱偁傞丅擔杮彂婭傗屆帠婰偺側偐偵偼棾捾尃尰側偳偲偄偆柤偺恄偼搊応偟側偄丅
僫僇僩儈僲僴儔僀
丂偦偺嫵愢偼乽愭戙媽帠杮婭乿乽擔杮彂婭乿乽屆帠婰乿偺嶰晹偺彂傪婎杮惞揟偲偟丄偲偔偵偦傟偧傟偺恄戙姫偵媑揷恄摴偺惛悜偑梋偡偲偙傠側偔帵偝傟偰偄傞偲庡挘偡傞丅
丂寭嬩偺恄摴偼桞堦恄摴偲徧偝傟偨丅偦偺柤徧偵丄寭嬩偺恄摴奅傪偍偺傟偺恄摴偱摑堦偟傛偆偲偄偆栰怱偲帺晧偑偙傔傜傟偰偄傞丅
僋僯僩僐僞僠僲儈僐僩
丂偙偺戝尦媨偵偁傠偆偙偲偐丄埳惃恄媨偺恄楈偱偁傞傾儅僥儔僗戝恄偑旘傃堏偭偨偲斵偼庡挘偟偨偺偱偁傞丅帪偺揤峜偵偙傟傪枾捄偝偊傕偟偨丅斵偼戝尦媨傪埳惃恄媨傛傝傕嫮戝側恄偺崙偲偡傋偔丄惌帯揑偵夋嶔偟偨偺偱偁傞丅
丂斵偼傒偢偐傜偺壠宯偺恄媉奅偵偍偗傞惓摑惈傪悽偵愰揱偡傞偨傔丄屆戙偐傜恄媉傪巌偭偰偄偨拞恇巵偺宯恾傪僩晹巵偺拞偵庢傝崬傫偩丅偙偺傛偆側側傝傆傝峔傢偸庤抜傪庢偭偰丄媑揷恄摴偼恄摴奅偺捀揰偵棫偭偨丅
僫
丂斵偑婎慴傪抸偄偨媑揷壠偺恄摴偼丄幒挰帪戙偵偼愴崙戝柤偺斴岇傪摼偨丅愴崙晲彨偑愴憟偺彑棙傪恄暓偵婩傝丄庺弍偵傛偭偰彑棙偺梊尵傪摼偰偄偨偙偲偼丄僲僲乕偺偲偙傠偱尒偨偲偍傝偱偁傞丅
僇僱儈
丂枊晎偼媑揷壠傪棙梡偟偰恄摴奅傪摑惂偟傛偆偲偟丄偦偺媑揷壠偼枊晎偐傜乽彅幮擨媂恄庡朄搙乿傪梌偊傜傟偰丄枊晎偺恄摴惌嶔偺庤愭偲側偭偨丅
丂暓嫵奅偵懳偟偰偼丄枊晎偼奺廆攈偵怗摢傪抲偐偣偰丄朄椷偦偺懠偺捠払帠崁偺揙掙傪恾偭偨丅摨偠傛偆偵丄恄摴奅偱偼媑揷壠偑掕傔傞恄幮偑怗摢偲側傝丄枊晎偺巜椷偑慡崙偺恄幮偵偔傑側偔峴偒搉傞傛偆偵側傞丅
丂壛偊偰彅幮擨媂恄庡朄搙偼丄姱埵偺側偄幮恖偼昁偢敀挘偺傒傪拝梡偡傞傕偺偲偟丄庪堖傗塆朮巕側偳偺拝梡偵偼媑揷壠偺嫋偟忬丄偄傢備傞恄摴嵸嫋忬傪梫偡傞偲婯掕偟偨丅屻偵偼偙偺婯掕偵堘斀偟丄嵸嫋忬偺岎晅傪庴偗偢偵憰懇傪拝梡偟偨応崌偺庢傝掲傑傝傕嫮壔偝傟偨丅
丂敀挘偲偼敀晍偺昞棤偵屝傪嫮偔傂偄偰巇棫偰偨偩偗偺庪堖偱丄婱懓偺廬幰傗壓恖偺憰懇偱偁傞丅
庪堖伻尨怓擔杮暈憰巎伾偐傜揮嵹
丂堦曽丄恄姱偺拝傞庪堖偼婱懓偑拝梡偡傞傕偺偱偁傞丅嫗搒嶰忦幒挰偁偨傝偺屶暈彜偐傜峸擖偡傞丅丂庪堖偼寴抧偵暥條傪埢栚偵尰偟偨搤梡偲丄幯抧偵巺傪婑偣偰暥條傪弌偟偨壞梡偑偁傞丅側偍偦偺暥條偵偼棫桹傗徏旽丄孮愮捁側偳崑壺側柾條偑怐傝弌偝傟丄巋廕傕偁傞丅
丂廆嫵偵偼憫尩偑昁梫偱偁傞丅幮恖偑壓杔偺拝偡傞敀挘偱恄偵廽帉傪曺偘偨傝丄鈹傪峔偊偰傕埿尩偼敽傢側偄丅傗偼傝幮恖偑塆朮巕偵庪堖傪拝梡偟丄庤偵鈹傪帩偪丄懌偵偼崟偄愺孊傪棜偒丄恄偵巇偊傞廳乆偟偄巔傪恖乆偵屩帵偡傞偐傜偙偦恄偺埿岝傕曐偨傟傞丅敀挘偱恄帠傪峴偊偲偄偆偙偲偼丄幮恖傪攑嬈偣傛偲偄偆偵摍偟偄丅
丂枊晎偺昡掕強偺埖偄傕庪堖偐敀挘偐偱埖偄偑堎側偭偰偄偨丅庪堖帒奿幰偼昡掕強偺墢偺忋偵拝嵗偱偒偨偑丄敀挘偼墢偵偼忋偑傟側偐偭偨丅摉慠丄枊晎偺嵸寛傕庪堖偵桳棙側傕偺偲側傞丅
丂偦傟偽偐傝偱偼側偄丅媑揷壠偼幮恖偨偪偵暯埨帪戙偺巵偱偁傞尮巵傗摗尨巵側偳傪柤忔傜偣丄壛偊偰榓愹庣丄愛捗庣偲偄偭偨庴椞柤傗敼恖惓丄媨撪彮曘丄媨撪彆側偳偺彅姱怑柤傪梌偊偨丅悽忋偱偼偙傟傪媑揷姱偲偄偭偨(側偍丄屆崱漭婰榐側偳傪彂偄偨暯嶳戧巵偺挿栧惓偺偙偲偩偑丄乽挿栧惓乿偲偄偆姱柤偼側偄丅偟偨偑偭偰乽挿栧惓乿偺柤偼丄惓妋偵偼乽挿栧庣乿偲偁傞傋偒偱偁傞丅偦傟傪乽挿栧惓乿偲偟偨偺偼丄廃杊偲挿栧傪巟攝偟偰偄偨栄棙斔偺挿栧庣偵墦椂偟偨偺偱偼側偐傠偆偐丅側偍偙傟偼搶戝巎椏曇嶽強偺嫶杮愭惗偵偛嫵帵傪偄偨偩偄偨)丅
丂偙傟傜偺姱怑偵偼偡偱偵偦偺惗柦傪幐偭偨棩椷惂偺屲埵丄榋埵偲偄偆姱埵偑偲傕側偭偨丅宍幃偺傒偺尃埿偱偁傞丅傕偪傠傫丄偙傟傜偼桳椏偱梌偊傜傟偨傕偺偩偭偨丅 丂師偺傛偆側帋嶼偑偁傞丅偁傞懞偺巵恄偺幮恖偺椺偱偁傞丅恄摴嵸嫋忬傪庼梌偝傟傞偨傔偵偼丄忋嫗偟偰媑揷恄摴偺摿孭傪庴偗側偗傟偽側傜側偄丅偦偺岎捠旓丄懾嵼旓丄庴椞柤傗姱埵傪摼傞旓梡偼丄偟傔偰侾俆椉偲偄偆丅
丂傑偨丄彑庤偵幮恖偵側傞傢偗偵偼備偐側偄丅偦偺恄幮傪巟攝偡傞斔庡偺悇慐忬傕昁梫偩偭偨丅偦偺幱楃傕偟側偗傟偽側傜側偄丅
丂惏傟偰恄姱偱偁傞偙偲傪媑揷壠偐傜嫋壜偝傟傟偽丄懞偺庡偩偭偨柤庡傗巵巕傪廤傔偰斺業偺墐傕奐偔丅
丂偄傑丄嬥堦椉傪幍枩墌側偄偟幍枩屲愮墌偲偡傞偲丄廫屲椉偼昐廫悢枩墌偲側傞丅偙傟偵忋偵婰偟偨傛偆側嶨懡側旓梡傪壛偊傞偲丄擇昐枩墌偐傜嶰昐枩墌傪梫偟偨偲偄偆丅拞彫偺幮恖偵偲偭偰偼夁戝側晧扴偱偁傞丅
丂偩偐傜懞偵傛偭偰偼丄懞恖偨偪偑崌椡偟偰傢偢偐偱偼偁偭偰傕镾暿偺宍偱丄憤妟堦椉埲忋偺嬥妟傪朢偟偄懞擖梡偱晧扴偟偰偄傞椺傕偁傞丅懞偵偲偭偰傕巵恄偺偙偲偲偼偄偊丄弌旓偑戝偒偄偲堿偱嬸抯傪偙傏偡幰傕偄偨傜偟偄丅
丂偦偺傎偐丄偄偔偮偐偺椺傪嫇偘傞偲丄恄幮崋傪嫋壜偝傟傞偺偵妟帤偲傕偱廫椉(栺俈侽枩墌)丄嵶偐偄偲偙傠偱偼塆朮巕拝梡偵嬥堦暘(栺侾枩俉愮墌)丄妡弿傗孊偺巊梡嫋壜偵傕偦傟偧傟嬥堦暘偑昁梫偩偭偨丅媑揷壠偵偼偙偺傛偆側奺暔昳偺壙奿傗嫋壜偵懳偡傞楃嬥偺儕僗僩偑嶌傜傟偰偄偨丅
丂媑尨戧巵偺巕懛偺偍戭偵偼丄暥壔俀擭(1805)偺傕偺偱偼偁傞偑丄嶰庬懢釶傪媑揷壠偐傜嫋偝傟偨偙偲傪帵偡彂椶偑巆傞丅
丂恄姱偼暥帤偳偍傝摢偺偰偭傌傫偐傜偮傑愭傑偱媑揷壠偵娗棟偝傟偰偄偨偙偲偵側傞丅
丂抧曽偺堦彫幮偵夁偓側偄棾捾尃尰偵傕媑揷壠偺埑椡偼妋幚偵壛偊傜傟偰偄偨丅偙傟傪帵偡傛偆側婰帠偑屆崱漭婰榐偵傕偄偔偮偐尒傜傟傞丅偦傟傪擇丄嶰徯夘偡傞丅
丂壝塱俀擭偺偙偲偩偑丄媑揷壠偐傜俀恖偺屼幏栶(媑揷壠偱抧曽恄幮傪娗棟偡傞幚柋扴摉幰)偑桼斾廻偵弌挘偟偰偒偨丅
丂偦偟偰俀恖偼埩尨孲壓偺幮恖慡堳傪椃廻偵屇傃弌偟丄斵傜偐傜偄偪偄偪恄幮偺宱塩忬嫷傪恞偹丄偐偮俀恖偐傜偼媑揷壠偺嵟嬤偺摦偒傗惌嶔側偳傪揱偊偰偄傞丅
丂俀恖偼桼斾廻偵廻攽偟偰偄傞偐傜丄偦傟側傝偺嫙墳偑側偝傟偨偙偲偼偄偆傑偱傕側偄丅
丂傑偨摨偠偙傠丄媑揷壠偺拕抝偑尦暈偟偨偺偱丄偦偺廽媀傪廤傔傞傋偔埩尨孲壓偺幮恖偵怗傟暥偑夢偭偨丅孲壓偺幮恖俀侽恖偑嫽捗偺幮恖戭偱夛崌傪奐偄偰偁傟偙傟嫤媍偺寢壥丄侾恖偁偨傝昐旸(堦旸廫暥偲偟偰堦娧暥)傪廤嬥偟偰偄傞丅偙傟偲偼暿偵廽媀傪帩嶲偡傞戙昞幰偺嫗搒墲暅偺椃旓側偳傕暘扴偟偰偄傞丅
丂偙偺傎偐慜偵傕婰偟偨傛偆偵丄幮恖偑戙懼傢傝傪偡傞偨傃偵嫗搒偵晪偄偰媑揷壠偱摿暿偺嫵堢傪庴偗偰偄傞丅漭婰榐偵傕戝榓庣惓掕偼偠傔埳惃庣惓岲丄戝榓庣惓師側偳暯嶳戧巵偺楌戙幮恖偺忋嫗婰帠偑偁傞偐傜丄傎偐偺扢朷寧巵傗晍戲戧巵側偳偺幮恖偨偪傕摨條偩偭偨偼偢偱偁傞丅
丂傑偨丄挿栧惓帺恎傕漭婰榐偺拞偵斵帺恎偑媑揷壠偐傜岎晅偝傟偨恄摴嵸嫋忬偺杮暥傪昅幨偟偰偄傞丅
丂媑揷壠偼偙偆偟偰峕屗枊晎偺尃埿傪屻弬偵恄埵偲恄崋偺庼梌尃傪撈愯偟丄偁傢偣偰恄姱偺曗擟尃傪庤拞偵擺傔丄嫮椡側恄怑摑惂傪幚巤偟偨丅偦偟偰慡崙偺幮恖傪嬥慘偲惂搙偺椉柺偐傜掲傔晅偗偨偺偱偁偭偨丅
嶳暁偨偪偺塣柦
丂嶳暁偵懳偡傞枊晎偺尩偟偄婯惂偼偲偳傑傞偲偙傠傪抦傜側偐偭偨丅丂枊晎偼帥堾偵憭媀傗暓帠傪攠夘偲偟偰擾柉偲帥抎娭學傪寢偽偣丄廆巪恖暿挔偺嶌惉傪帥堾偵柦偠偨丅偦偺憭媀傕帥堾偺傒偵嫋偟偨丅暓嫵傪帥堾偵撈愯偣偟傔偨丅偦偺寢壥丄嶳暁偼暓嫵偐傜掲傔弌偝傟傞偙偲偵側傞丅
丂懠曽丄嶳暁偑幮恖偵側傠偆偲偟偰傕丄媑揷恄摴偵傛偭偰恄怑偼尩廳偵摑惂偝傟偰偄傞丅偦偺媑揷恄摴偼慡崙偺恄幮偺娗棟尃傪暓嫵帥堾偐傜扗偭偰丄恄怑偵梌偊傛偆偲偡傞丅
丂偦偟偰丄摉慠偺偙偲偱偁傞偑丄暓嫵懁偑偄偆杮抧悅鐟愢傗恄暓廗崌傪斲掕偡傞丅杮抧悅鐟愢偑偁傞偑屘偵丄恄摴偼暓嫵偺壓晽傪庴偗丄憁椀偑暿摉側偳偺抧埵偵偁偭偰丄恄幮偵曭巇偡傞幮恖傪妠巊偟偰偄傞丄偲偄偆偺偑媑揷壠懁偺尵偄暘偱偁傞丅暓嫵懁偼暓偑庡偱恄偑廬丄偄傢備傞暓杮恄鐟偱偁傞丅
丂媑揷恄摴偼偙傟偑娕夁偱偒側偐偭偨丅桞堦恄摴偺柤偺偲偍傝丄恄摴傪暓嫵傛傝桪埵偵抲偔偙偲偑媑揷恄摴偺暓嫵懳嶔偩偭偨偺偱偁傞丅偙偪傜偼恄偑庡丄暓偑廬偺恄杮暓鐟偱偁傞丅
丂幚慔廆嫵偲偟偰丄嫵媊傕枮懌偵帩偨側偄廋尡摴偺嫆傝強偼恄暓廗崌偱偁傞丅(廋尡摴偑偦偺嫵棟傪棟榑壔偟偰丄乽栘梩堖乿乽摜塤榐帠乿偼偠傔丄奺庬偺嫵媊彂傪曇傓傛偆偵側傞偺偼峕屗帪戙屻婜偱偁傞丅偄偄偐偊傟偽丄廋尡摴偑悐戅偟偨屻偵丄偙偺傛偆側懱宯揑側彂暔偑惉棫偟偨偺偱偁傞丅廋尡摴偑枊晎偐傜婯惂傪庴偗丄幚慔柺偑戝偒偔惂尷偝傟偨偨傔偵丄壣偑偱偒偨偺偩)丅廋尡摴偵偁偭偰偼乽恄偐暓偐乿偲偄偆娤擮偼側偄丅偁傞偺偼乽恄傕暓傕乿偱偁傞丅偦傟偑摉帪偺弾柉偺姶妎偱傕偁偭偨丅弾柉偵偲偭偰偼乽恄偐暓偐乿傛傝傕屼棙塿偺桳柍偱偁傞丅尰悽棙塿偱偁傞丅嶳暁偼偦偺弾柉偺梸媮偵摎偊傞廆嫵幰偩偭偨丅
丂偲偙傠偑媑揷恄摴偼廋尡摴傪斲掕偟丄恄傪桪埵偵抲偔丅懠曽偱暓嫵偼暓傪桪愭偡傞丅暓嫵偲媑揷恄摴偺娫偵偁偭偰嶳暁偼丄椉幰偐傜抏偒弌偝傟偰偟傑偭偨偺偱偁傞丅
丂嶳暁偼媑揷恄摴偺巟攝壓偵擖偭偰幮恖偲側傞偐丄恀尵廆傗揤戜廆偵夵廆偟偰憁椀偵側傞偐偟偐側偔側偭偨丅傕偟俀偮偲傕嫅斲偡傟偽丄嶳暁偼偨偩偺柉娫偺攓傒壆偵懧偡傞丅堦夘偺婩摌巘偵棊偪傇傟傞偺偱偁傞丅屩傝崅偄嶳暁偵偼懴偊傜傟傞偙偲偱偼側偐偭偨丅
丂偵傕偐偐傢傜偢丄恄暓偳偪傜偵傕梌偡傞偙偲偑偱偒側偄傑傑偵棊楫偟偰偄偭偨嶳暁偼懡偐偭偨偼偢偩丅堜尨惣掃偺彫愢偵傕乽巇妡偗嶳暁乿偺柤偱偵偣嶳暁偑搊応偡傞丅岇杸抎偵嵶岺傪巤偟丄嵓媆傑偑偄偺婩摌傪偟偰偄偨丅尦椢偺崰偵偼偙偺傛偆側夦偟偄嶳暁偑墶峴偟偰偄偨丅偦偟偰斵傜偑偝傜偵棊偪傇傟傞偲丄嵳暥岅傝傪偼偠傔丄偪傚傫偑傟傗垻曫懮梾宱側偳偺寍擻偵傛偭偰丄栧晅偗傪偟側偑傜奺抧傪夢傝丄嵶乆偲惗妶傪棫偰傞傛偆偵側傞偙偲偼擔杮寍擻巎偺婰偡偲偙傠偱偁傞丅
尃暫奨堦懓偺懳墳
丂偦傟偱偼尃暫塹偼偠傔朷寧巵傗戧巵偼偳偺傛偆偵偙傟偵懳墳偟偨偺偩傠偆丅丂枊晎偑嶳暁偺婯惂傪嫮壔偟丄媑揷恄摴偑恄摴奅傪巟攝偟巒傔偨姲暥偲偄偆帪婜偵丄尃暫塹偲摗暫塹偼棾捾尃尰偐晉巑懞嶳廋尡偐偱憟偭偨偺偱偁傞丅
丂寢壥偼尃暫塹攈偺彑棙偲側傝丄姲暥墢婲偲扢宯恾偑嶌惉偝傟丄尃暫塹偑斵偵忔傝堏偭偨棾捾尃尰偺幮恖偱偁傞偙偲傪晍戲懞傗暯嶳懞丄崟愳懞側偳抧尦偺懞恖偨偪偵彸擣偝傟偨丅攕傟偨摗暫塹偼捛曻偝傟偰晉巑嶳榌偵嫀偭偰峴偭偨丅
丂尃暫塹偼嶳暁偐傜幮恖偵曄恎偡傞偙偲偵偲傕偐偔傕惉岟偟偨偺偱偁傞丅怘偄媗傔偨嶳暁偲偟偰丄恖乆偐傜層嶶廘偄栚偱尒傜傟偨傝丄寉曁偝傟偢偵偡傫偩偺偩偭偨丅
丂偦偟偰尃暫塹偲斵偺堦攈偼丄棾捾嶳忋偵彫偝偄側偑傜傕弜壨偵偍偗傞孎栰椉強尃尰偺揱摑傪庴偗宲偄偱丄棾捾尃尰偺幮傪寶偰傞偙偲偑偱偒偨丅偦傟偑尰嵼傕巆傞墱偺堾側偺偱偁傞丅偦偺墱偺堾偺娾偼椉強尃尰偑偼偠傔偰孎栰偵崀傝偨偲揱偊傞僑僩價僉娾偵尒棫偰偨傕偺偱偁傞丅
丂宑挿侾俀擭(1607)偺暥彂偵偁傞傛偆偵乽偙偺嶳偼揤嬬偺偡傒偐偩偐傜丄旕忢偵峳傟偰偄偰丄堦棦巐曽偵擖偭偰棃傞幰偼偄側偄乿偲偄偆偺偼丄斵傜偑忋偭偨棾捾嶳偺摉帪偺忬嫷傪尰偟偰偄傞偲偄偊傛偆丅孎栰嶰嶳偺惃椡偑丄弜墦椉崙偐傜揚戅傪梋媀側偔偝傟偨偁偲丄恖傕擖傜偢峳傟曻戣偵側偭偰偄偨偺偱偁傞丅
丂傑偨丄屼杮幮憿塩擵妎挔偼丄尃暫塹揱愢傪婰偟偰偐傜丄乽媨拰棫偰乿偁傞偄偼乽媨拰懢晘偔棫偰乿偲彂偄偰偄傞丅乽懢晘偔乿偼暥忺偲偟偰傕丄弶傔偰棾捾尃尰偺彫幮傪寶偰偨帠忣傪暔岅傞傕偺偱偁傞丅
丂棾捾嶳偼奀敳愮嘼傪墇偊傞丅寛偟偰廧傓偺偵堈偟偔側偄丅嫃廧偺帺桼傪扗傢傟丄棾捾尃尰偺幮恖偲偟偰惗偒傞偨傔偵偼丄搤偺姦偝偺尩偟偄棾捾嶳拞偱曢傜偝偞傞傪摼側偄丅偟偐偟丄偳傫側偵昻偲姦偵嬯偟傕偆偲傕丄姲暥墢婲偵偁傞傛偆偵尃暫塹偨偪偼棾捾尃尰偺戸愰偵廬偭偰丄偙偺恄偵曭巇偟側偗傟偽側傜側偐偭偨偺偱偁傞丅 丂偦傟偽偐傝偱偼側偄丅棾捾尃尰傪巟偊傞傋偒晍戲懞丄扢懞丄暯嶳懞側偳傕昻偟偐偭偨丅偄傑暯嶳傪椺偵庢傠偆丅
丂暯嶳偱偼峕屗帪戙丄侾擭傪捠偠偰暷傪怘傋傜傟偨壠偼丄傢偢偐俀尙偩偭偨偲偄偆丅偦偺摉帪丄暯嶳偺悽懷悢偼栺俆侽偐傜俇侽尙丅偦偟偰丄師偺傛偆側榖偑揱傢傞丅
丂傑偩丄戧巵堦懓偑棾捾嶳拞偵廧傫偱偄偨崰丄暷傪攦偆偨傔偵堦懓偺幰偑偲偒偳偒壓嶳偡傞偙偲偑偁傞丅幮偐傜傕偭偲傕嬤偄暯嶳偵偼暷偑側偄丅傗傓傪摼偢丄幮恖偺壠懓偼昐惄偐傜庁傝偨栰椙拝偵拝懼偊丄幮恖偱偁傞偙偲傪塀偟偰丄暷傪媮傔偰棦偵壓偭偰偄偭偨偲偄偆丅
丂師偺傛偆側榖傕偁傞丅
丂棾捾嶳偐傜朷寧巵丄戧巵堦懓偑傢偐傟偰扢丄媑尨丄暯嶳側偳偵嶶偭偨偲偒丄暯嶳偵壓傝傞戧巵偵暯嶳偺懞恖偼忦審傪晅偗偨丅
丂偦偺忦審偲偼暯嶳偱偼偲偰傕戧巵傪庴偗擖傟傞偩偗偺宱嵪揑側梋桾偑側偄丅偩偐傜丄暯嶳傊偺堏廧偼擣傔傞偑丄懞恖偑埶棅偡傞婩摌傗塽昦棳偟偼偡傋偰柍椏偵偣傛偲偄偆傕偺偩偭偨丅
丂戧巵偼暯嶳懞柉偺梫媮傪庴偗擖傟偨丅埲屻丄楌戙偺幮恖偨偪偼挿旜愳偺乽憲傝恄偺暎乿(偙偺暎偼暯嶳懞偲椬懞偺挿旜懞偲偺嫬奅偵嬤偄)偱塽昦棳偟傗奞拵憲傝傪峴側偭偰偒偨丅
丂偙偺傛偆側榖偑惗傑傟傞偙偲偼丄暯嶳偼傕偪傠傫偺偙偲丄棾捾嶳拞偺崲擄傪嬌傔偨惗妶傪暔岅傞傕偺側偺偩丅
丂尃暫塹偼偠傔朷寧巵傗戧巵偼偙偆偟偨尩偟偄娐嫬偺拞偱丄棾捾尃尰偺幮恖偲偟偰偺戞堦曕傪摜傒弌偟偨偺偱偁傞丅
丂偲偙傠偱丄塽昦棳偟偱偁傞偑丄堛妛偺敪払偟偰偄側偄摉帪丄傂偲偨傃棳峴傝昦偑敪惗偡傟偽丄堦懞慡柵偺嫲傟偡傜偁偭偨丅塽昦棳偟偺偲偒偼丄懞拞偺恖乆偼壠乆偺尙愭偵傓偟傠傪晘偄偰偦偺忋偵惓嵗偟丄恀寱側昞忣偱乽憲傝恄偺暎乿偵岦偐偆幮恖偺偍釶偄傪庴偗丄偦偟偰丄懞偺彲壆埲壓嶰栶偑幮恖偵偮偒廬偭偰偄偨偲偄偆丅
媑揷恄摴偑梫媮偡傞恄奿偺曄峏
丂偟偐偟丄棾捾尃尰偺幮恖偲偟偰偺尃暫塹堦懓偺嬯楯偼偙傟偩偗偱偼廔傢傜側偐偭偨丅丂帪戙偑壓偑傞偵偮傟偰丄枊晎偲媑揷恄摴偺嶳暁晻偠崬傔偲傕偄偊傞惌嶔偑傑偡傑偡嫮峝側傕偺偲側偭偰備偔丅
丂媑揷恄摴偼棾捾尃尰偵恄奿偺曄峏傪媮傔偰偒偨偺偱偁傞丅
丂媑揷恄摴偺崻杮惞揟偲偄偆傋偒彂暔偼乽愭戙媽帠杮婭乿乽擔杮彂婭乿乽屆帠婰乿偺嶰彂偱偁傞偙偲偼慜偵傕怗傟偨丅偙偺嶰晹彂偵偼揤屼拞庡恄偐傜巒傑傝丄敧昐枩偺恄乆偲屇偽傟傞傛偆偵幚偵懡偔偺恄乆偑婰嵹偝傟偰偄傞丅
丂偲偙傠偑丄懞偺峀応偺曅嬿傗嶳摴偺朤傜傗嫄栘偺崻尦側偳偵偼丄恄摴嶰晹彂偵搊応偟側偄嶨懡側恄偑釰傜傟偰偄偨丅崱擔偱傕悢偼彮側偔側偭偨偲偄偆傕偺偺丄嶳懞傗擾懞偵偼柤傕抦傟偸恄傪釰偭偨釱偲偟偐屇傃傛偆傕側偄彫偝側幮偑偁傞丅
丂偙偺傛偆側彫偝側恄乆偼丄偦傟傪怣偢傞恖偨偪偺捈愙偱擔忢揑側婩傝偺懳徾偵側傞恄乆偩偐傜丄柤慜側偳偼偳偆偱傕傛偐偭偨丅偳偆偱傕傛偐偭偨偲偼尵偄夁偓偩偑丄偦傟傎偳娭怱傪帩偨側偐偭偨丅帺暘偨偪偺擸傒偵偨偩偪偵墳偠丄偦傟傪夝寛偟偰偔傟傞恄偱偁傝偝偊偡傟偽傛偐偭偨偺偱偁傞丅昦婥傗夦変偺偡傒傗偐側姰帯丄暔偺夦偺戅嶶丄奞拵嬱彍丄杺彍偗丄奜晹偐傜怤擖偡傞嵭偄傪杊偖丄側偳側偳偱偁傞丅偩偐傜丄偛恄懱偼幹偩偭偨傝丄屜偩偭偨傝偡傞偙偲傕偁傞丅彫愇偺傛偆側椺傕懡偄丅
丂姍憅帪戙偵忩搚恀廆傪奐偄偨恊阛偼丄愢朄傪暦偒偵棃偨榁庒抝彈偵恄媉晄攓傪孞傝曉偟愢偄偨丅
丂垻栱懮擛棃傪怣怱偡傟偽壗傕嫲傠偟偄傕偺偼側偄丄恄偵棅傞側偲偄偆偺偑斵偺庡挘偩偭偨丅栱懮偺帨斶傪変偑恎偵偄偨偩偗偽丄傕偭偲傕嫲傞傋偒巰傪傕嫲傟傞傕偺偱偼側偄偲孞傝曉偟偨丅偟偐偟丄恖乆偼垻栱懮擛棃偺傎偐偵恄傪怣偠傞偙偲傪傗傔側偐偭偨丅
丂嵟屻偵偼恊阛偺傎偆偑崻晧偗偟偰丄擮暓傪彞偊傞幰偵偼恄偺壛岇偑偁傞偲偄傢偞傞傪摼側偐偭偨丅弾柉偑柤傕側偄恄乆偵婑偣傞嶨懡側怣嬄偵偼崻嫮偄傕偺偑偁偭偨偺偱偁傞丅
丂偟偐偟側偑傜丄擔杮彂婭偺憇戝側恄偺懱宯偵慻傒崬傑傟偨桼弿惓偟偄恄乆偱偼丄恖乆偺偝傑偞傑側婅偄偵偼懄嵗偵懳墳偱偒側偄丅恄乆偑慻怐壔偝傟丄暘嬈壔偟偰偄傞偐傜丄懡悢偺恖乆偺帩偮偄傠偄傠側梫朷偵偼晀懍偵墳偠偒傟側偄偺偩丅
丂偲偙傠偑丄媑揷恄摴偼偙偺傛偆側恖乆偺慺杙側恄怣怱偺幚懺傪柍帇偟丄恄幮偵懳偟偰嶰晹彂偺恄乆埲奜偺恄傪擣傔側偔側偭偨偺偱偁傞丅擔杮彂婭傗屆帠婰偺側偐偵偼棾捾尃尰側偳偲偄偆柤偺恄偼搊応偟側偄丅
丂帪戙偼偡偱偵姲暥擭娫偐傜栺俉侽擭傪宱夁偟丄尃暫塹巰屻偺帪戙偱偁傞丅尃暫塹偺巕懛偺朷寧巵偲戧巵偑丄媑揷恄摴偺恄奿曄峏偺梫媮偵懳墳偟偰庢偭偨庤抜丄偦傟偑偙傟偐傜弎傋傞墑嫕墢婲側偺偱偁傞丅